「彩都の水」に含まれている注目のメタケイ酸て何?
「彩都の水」にはメタケイ酸が豊富に含まれています。泉質名としてはあまりなじみのない言葉ですが、最近では、この成分の研究が進められており、とても注目を浴びています。
簡単に言ってしまうとメタケイ酸とは、温泉に含まれている天然の保湿成分のことです。
しかも飲料水として利用できる水はたいへん貴重なものと言われています。
「メタケイ酸」が注目を浴びる理由として下記のような効果があると言われています。
■天然の保湿成分がたっぷりで肌に良い
■肌の新陳代謝を促進する
■コラーゲンの生成する働きがある
■毛髪や爪を強くする
■皮膚の老化の抑制する
■胃の粘膜を修復する作用がある
■コレステロールを排出しやすくする
■動脈硬化を和らげる効果がある
このように美容成分はもちろんのこと、健康成分も大きな要素がある成分が豊富に含まれている「彩都の水」は癖がなく、すごくマイルドで美味しい水です。ぜひ毎日の生活に取り入れてみてください。

⛄臨時休業のお知らせ⛄
寒波の影響をうけ吐水口凍結対策を講じておりますので、2021年1月8日(金)・9日(土)は臨時休業とさせて頂きます。日頃よりご飲用頂いておりますお客様にはご迷惑をお掛けしますが何卒よろしくお願い申し上げます。
福茶
お正月や新春には「福茶」もしくは「大福茶」と呼ばれるお茶をいただく習慣が残っています。主に関西でよく見られるもので、他の地域では少し珍しい習慣かも知れません。
この「福茶」は、昆布と梅干しのいずれか、あるいは両方が入ったお茶で縁起ものと言われています。
また節分の際にも、上記に豆まきに使った豆を三粒ほど入れ飲んでいる場合もあります。
実は、歴史はとても古く946年当時、在位した村上天皇が毎年お正月に梅干し入りのお茶を飲んだことから広まったと言われています。
当時、天皇が一服するお茶ということで「皇服茶」と呼ばれていたようです。
縁起物としてはもちろん、お酒を飲みすぎた時にも「福茶」はおすすめです。
ミネラルたっぷりの昆布と、胃腸を守る梅干しが、二日酔いや、飲みすぎ・食べすぎに大きな効果があります。
特別な製法やレシピはなく、煎茶に昆布と梅干しを入れるだけです。
お好みの分量や配合を追求してみたりと、各家庭ならでは「福茶」を楽しんで見つけてください。
縁起物として飲む場合は、1年の無病息災をお祈りしながらいただきましょう。
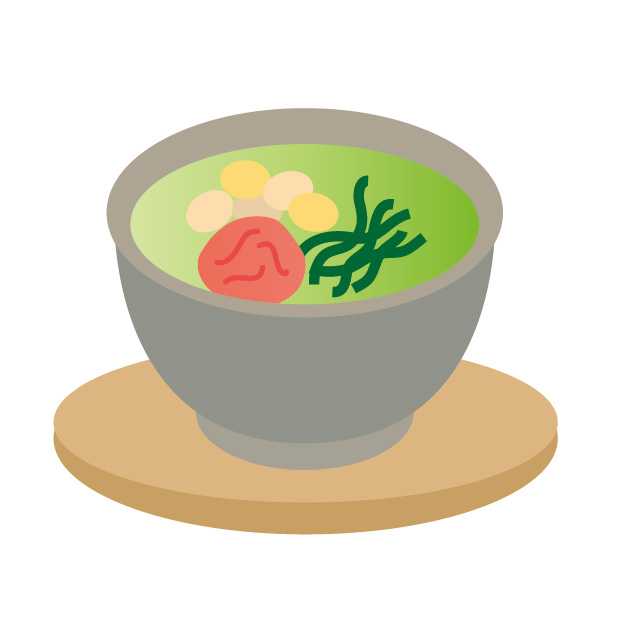
野外活動に欠かせない大切な水
新型コロナウイルスの感染リスクを考え、混雑しそうな場所は避け、野外活動(キャンプや登山など)を行う人が増えてきました。野山などは「3密」になりにくく、自然に囲まれてリラックスできるということもあるようです。
様々な準備物が必要になりますが、中でも水は登山やキャンプにおける基本装備の一つです。
水がないだけで体内は水分不足に陥り、低体温症を招いたり、登山するにも力が出ないといった事になりかねません。
このように山では水は欠かせないものですのでしっかり常備持参したり、水場スポットを調べておくことは重要です。
雪山のキャンプでしたら、雪を溶かして水を作ることもできます。
この場合、まずは出来るかぎり、綺麗な雪を探すことから始めましょう。
この時は、足元にしっかり気を付けて、少し登山道から外れた安全な場所で雪を掘るのがポイントです。
そして雪をバーナーなどで溶かします。雪の中には自然界の不純物が多く混じっていますので溶かす途中でスプーンなどで取り除いてください。小さいものはコーヒーフィルターなどを使い、ろ過するとばっちりです。
これで水ができあがります。
冬は水場が凍って使えないことや想定外の山行時間で、水場のある場にたどり着けないなんてことも多々あります。
水をしっかり常備して、安心安全な野外活動を行ってください。

冬における植物の正しい水やり
秋に澄み渡った水は、寒さが増してくるにしたがいより磨きがかかり、研ぎ澄まされていく。暖かい時分の水は、生命の輝きを放っているが、冬のそれは命を脅かす厳しさを持っている。
(中村草田男 「長子」より)
冬の寒さの中に厳しさが有ることが、容易に想像できる有名な一節です。
私たちはもちろんのこと、植物達にとっても過ごし難い季節になります。
よく冬の霜がおりた朝、植物の葉には氷がついているのを見かけませんか?
実はこれ、細胞の内部が凍ってしまうことを防いでいるケースもあるのです。
氷点下の冬を過ごす植物は、体内の凍結を回避したり、あるいは凍結しても生きられる強さを持っている一面があります。
それでも気になる冬の水やり・・・どのようにすれば良いのでしょうか。
■水やりは、土の表面が乾いたら行うことが基本です。
■乾いて2~3日たってからの午前中に与えます。
※水やりは頻度が多いと、根を腐らせるます。
※夕方以降の水やりは夜間の冷えにより、凍る可能性もあるため避けてください。
※観葉植物は水やりとは別に霧吹きで葉に水分を与えてあげましょう。
■水やりの水は15度くらいが適温です。
※汲み置きして常温にするなど工夫してみてください。
水やりに時に神経質になる必要性はほとんどありません。
植物の種類によって耐えられる温度や育て方は異なりますが、基本に注意して、植物の冬越しを行いましょう。

お米を美味しくする水
海の幸、山の幸・・・ついつい食べ過ぎてしまう「食欲の秋」ふっくらやわらかくて粘りがあり、格別のおいしさを感じられる新米収穫のシーズンです。
私たちの主食であるお米。
実は、お米を研ぐ際に1番最初に使用するお水がご飯の美味しさを左右すると言われています。
乾物であるお米は、水につけた瞬間にお米が吸収できる水分のうちの7割程度を吸い込んでしまうのです。
なので研ぐ際に最初に使用するお水に、彩都の水、ミネラルウォーターなどを使用してみてください。
ポイントは最初に使用する水なので、2回目以降の研ぐ水は水道水でも構いません。
たったこれだけで新米も、いつものお米も、よりおいしく炊けるようになります。
さらに、こだわるなら、お米を炊くときも彩都の水やミネラルウォーターなどを使用するとよりベストです。
また、入れた後すぐに炊かずに30分ほどお米を浸水させると、水分がお米にしっかりと吸収され、お米の中に水が浸透しやすく、さらにふっくらと炊き上がります。
「彩都の水」なら長時間保温すると出てくる黄ばみを温泉成分により抑える効果もあります。
是非、試してみてください。

水でリラックスしましょう
水には、いろんなリラックス効果があると言われています。水を上手に取り入れたリラックス方法がたくさんありますので是非、参考にしてください。
【飲んでリラックス】
コップ1杯の水を飲むとリラックスできて寝られるようになる、緊張した際に水を飲んで落ち着かせる・・・と聞いたことはありませんか?
水を飲むことでリラックスできるという理由は、水に含まれるカルシウムやマグネシウムによる鎮静作用によるものと言われています。
是非、彩都の水でリラックスしてください。
【聞いてリラックス】
川のせせらぎや波の音、雨音など水が奏でる音を聞いていているだけでなぜか癒され、気持ちがだんだん穏やかになってくる。
実は、水の流れる音には「1/fゆらぎ」と呼ばれる人の心をリラックスさせる効果を持つ波形が含まれています。
※「1/fゆらぎ」とは、「規則的」なものと「不規則」なものが調和した状態のことを言います。
だから水が奏でるメロディーを聞くことで、日常のストレス・不安・耳鳴りを緩和し、深い眠りを誘ってくれるようになる効果が期待できます。
【見てリラックス】
水には、なんと視覚的にも癒し効果があることも判明しています。
水の癒しは自然の中だけに存在するわけではありません。
「水族館」「噴水のある公園」など身近に存在する水スポットに出かけて癒されてみてはいかがでしょうか
外出する時間がないという方には、水を使った様々なインテリアを部屋に飾ってみたり、波の音などが収録されたヒーリングCDなどを活用してみてください。
きっと心を落ち着かせ、和ませてくれます。

水をたっぷり使った冷たいお菓子
暑い夏に最適なお菓子といえばアイスクリームやかき氷はもちろんですが、やはり冷たくひんやりしたものを食べたくなりませんか。今回は、美味しい水をたっぷり使った、夏にピッタリな簡単お菓子のレシピをご紹介します。
【透明感たっぷり!水ゼリー】
(材料4~5人分)
・彩都の水 600ml
・粉寒天 2g(小さじ1)
1. お鍋に彩都の水と粉寒天を入れて5分おく
2. 火にかけて沸騰してきたら弱火に
3. 3分ほど弱火のままかき混ぜる
4. 火を止めてから、お気に入りの容器に流し入れる
5. 冷蔵庫で半日冷やす
いろんなフルーツを入れたりのアレンジもおすすめです。
簡単でとっても美味しいですよ。
【のどごし最高!ひんやり水ようかん】
(材料6人分)
・彩都の水 400ml
・角寒天1/2本
・上白糖150g
・さらしあん50g
1.鍋に彩都の水を入れ、粉寒天を加えてよく混ぜ、火にかけてさらに混ぜながらとかす。
2. 上白糖を加え溶かし、1~2分煮る。
3. 火を止め、こしあんと塩を加え、なめらかになるまでよく混ぜる。
4. 粗熱が取れたら水でぬらした流し型に流し入れ、冷やしかためる。
5. かたまったら食べやすい大きさに切り、器に盛る。
どちらも美味しく仕上げる秘訣は水。
ぜひ美味しい水で作ってみてください。

夏の正しい水分補給
これからの季節、ニュースなどでも耳にすることが多くなる脱水症・熱中症・熱射病。夏場は汗をかく分、特に意識して水分の摂取を心がける必要があります。
しかし水分補給として一度に大量の水を摂取すると、かえって体内の電解質バランスを崩して体調不良を引き起こしてしまいます。
これは大量の発汗によってナトリウム、つまり塩分がいつもより大量に失われてしまっているからです。
そこで体内の塩分や糖分のバランスを整えるために、水分だけでなく汗で失われる塩分(ナトリウム)の補給も必要になってくるのです。
水分補給の量は、かいた汗の量を目安にしてください。
塩分(ナトリウム)補給は、水と一緒に塩昆布や梅干しなどがおすすめです。
その他、ナトリウムが含まれたキャンディーやイオン飲料などもたくさん発売されていますので、上手に活用してください。
特に抵抗力の弱いお子さんが口にするものは何より安全性を第一に考えたいですね。
そして過酷な夏を経験するのは、私たち人間と同じく植物だって同様です。
植物は根から水分を吸収し、葉や幹(茎)からの蒸散作用によって水分を放出しています。
日照りなどによって吸収より蒸散の方が上回ると、葉がしおれ、落葉し、枯れてしまいます。
夏期の直射日光が強い日中には、葉や茎が焼けてしまうので絶対水をかけないようにしてください。
7月〜9月の日照りが続くようなときは、1日に2回(朝・夕方)の水やりが必要です。
朝方は午前9時頃までに、夕方は午後5時以降にやるとよいでしょう。
お庭などがあるご家庭は参考にされてください。
正しい水分補給で暑い夏を乗り切りたいですね。

恵みも豪雨ももたらす梅雨
もうすぐ雨の降り続く梅雨がやってきます。2020年の梅雨予想は、全国的には、平年よりも早い梅雨入りとなる一方、短期間で終わるのではないかと言われています。
5月31日には、四国の梅雨入りを発表されましたが、昨年より26日早く、5月の梅雨入りは2013年以来7年ぶりとなるそうです。
気になる雨量は平年並みか少し多い予想が立てられていますが、前線が停滞する日が多くなると予想され大雨に警戒したいところです。
そんな梅雨。
ジメジメした日が続く季節になりると、仕事でもプライベートでも外に出るのが気が重くなり憂鬱な気分になりがちですが、
意外にも梅雨がもたらすメリットがたくさんあります。
まず「水不足」です。
農作物の成長はもちろんのこと、雨に埋もれた落葉が腐敗して腐葉土になり、土壌を豊かにし、その栄養分が川に流れ出し、川や海のプランクトンに、そのプランクトンを食べて魚が成長します。
このように自然への恩恵は計り知れません。
また"雨が落ちる“しとしと”という音は、リラックスの効果があるそうです。
この雨音の心地よいリズムが自然と心を落ち着かせ、脳内の集中力がアップします。
仕事の生産性が晴れの日よりも高まるので、デスクワークやテレワークにも最適ですね。
そして美容にも良いとされています。
お肌にいいとされる湿度は65%。梅雨どきは常にこの湿度を保っている日が多いため、老化の原因となる乾燥を防いでくれます。
また雨により、町中にマイナスイオンが広がります。
マイナスイオンとは、空気中に含まれるわずかな電気を帯びた分子集団のことを言いますが、血液の浄化作用、細胞の臓活作用、抵抗力の増進作用、自律神経の調整作用など4つの作用があり人の健康を積極的に助けてくれる事がわかっています。
鎮静・催眠・制汗・食欲増進・血圧降下・疲労防止・疲労回復などの相乗効果も期待できます。
雨音に耳を傾けて、心を落ち着かせ自然を楽しんでみてはいかがでしょうか。


